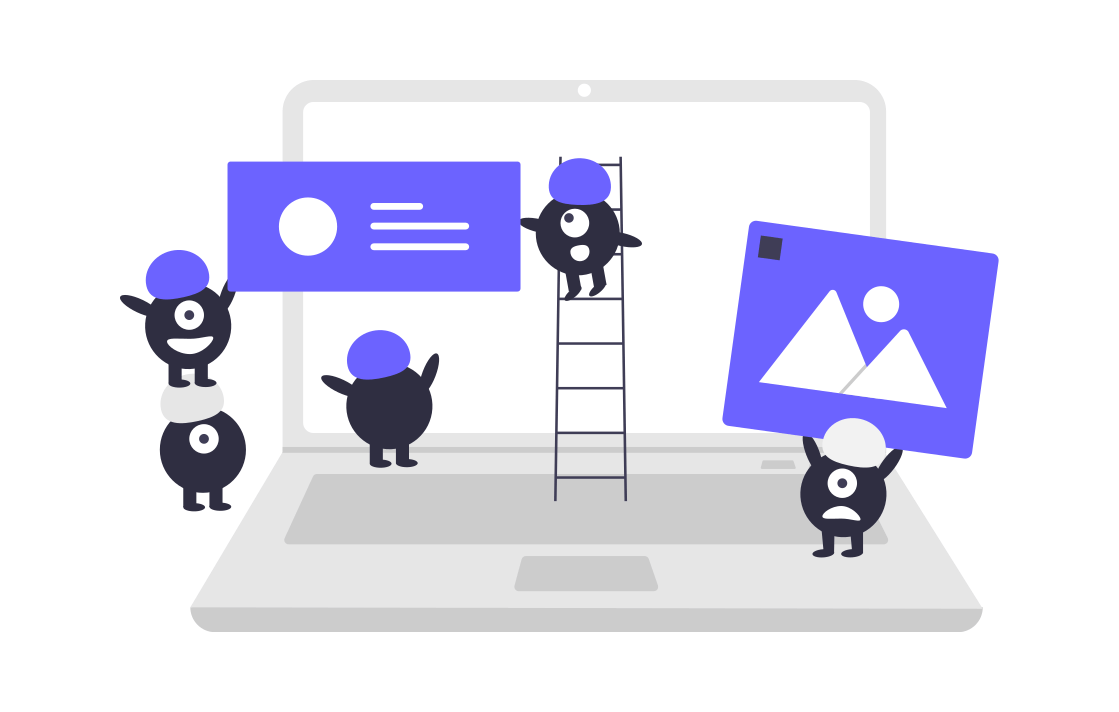今回、プログラミング初心者の方ITやプログラミングに興味のある学生を対象にpythonの関数の使い方、引数、返り値についてご紹介します。
もし良ければ、python文法 第一弾もご参照ください。
関数
関数を用いると複数行のコードをひとまとめにすることが可能になります。
pythonで関数を使う場合、以下のように記載します。
def 関数名
def hello(): # helloが関数名 a = 2 b = 3 print(a + b) hello() # 関数の呼び出し
上のコードのように関数を使った場合、表示結果は5になります。
引数
また関数を使う時に引数を使うことがあります。
引数とは関数に渡す値のことを指します。
例えば、以下のように記載すると
hello(2, 3) の2と3を引数として関数名helloに渡します。
関数の中で計算の処理がされ表示結果は5になります。
def hello(a,b): # a、bが引数 print(a + b) hello(2, 3) # 引数として2と3を渡す
返り値(戻り値)
引数とセットで覚えた方が良いのが返り値(戻り値)です。
返り値とは引数を関数に渡し、関数の中で処理された結果のことを指します。
pythonではreturnを関数内に記載することで返り値が使えます。
def hello(a, b): # a、bが引数 つまり3と4が引数としてきます。 r = a + b return r # rが返り値 k = hello(3, 4) # 返り値として受け取った値をkに入れる print(k)
上記のコードの場合、hello(3,4)の3と4を引数としてhello関数に渡します。
関数の中では足し算が行われ、その結果がrに代入されます。そのrの結果を返り値として返します。
なので、表示結果は7になります。
プログラミング初心者の場合、引数と返り値のイメージが湧かず理解するのが難しいと思いますが、
プログラミングをしていく上で必要な知識なので、徐々に慣れていくと良いと思います。
引数と返り値については以下のサイトを見るとめちゃくちゃイメージが湧きやすいと思いますので、よければご参照ください。